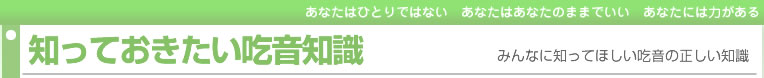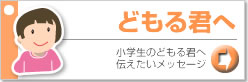吃音の予期不安、場面恐怖、吃語恐怖
» はじめに
伝統的な吃音治療が吃症状にのみ目を向けてきたことに対して、アメリカのアイオワ学派の人々は厳しく批判した。症状にのみ意識を集中することによって、吃音にとって最大の問題である不安や恐れをますます強めることになると考えたからである。成人吃音者に共通する感情は、不安と恐れである。それが吃音問題を複雑にし、大きなものにしていく。この吃音の不安と恐れについて考えていこう。
» 吃音予期闘争説
吃音原因論の中に、吃音予期闘争説がある。吃音者は、話す前に、うまく話せないと考え、そのために発語器官の筋肉が緊張し、話すことを躊躇する。つまり、話すことを妨げる行為から吃音が起こると、吃音予期闘争説は説明する。
ブルーメルは、子どもの吃音は、自分が吃っているという自覚もなく、筋肉の緊張もない音の繰り返しや引き伸ばしで始まるとし、一次吃と名づけた。
「ボボボボクネ、アノーネ」のような話し方に対して、「ゆっくり言ってごらん」などの注意を周りがすると、子どもうまく話そう、うまく話せないかもしれないという反応を示すようになる。このように、話す時に不安や恐れを伴う吃音を二次吃と名づけ、吃音が予期闘争反応となるのは、この二次吃においてだと説明した。
ジョンソンは、ブルーメルが一次吃と名づけたものは、正常な幼児のことばのなめらかでない話し方と変わらないとし、子どもが予期闘争反応を示すようになるのは、子どものせいではなく、両親の子どもに対する異常な反応に原因があると主張した。
シーアンは、二重接近-回避型の抗争として吃音を説明した。話したいという欲求と話したくないという欲求、黙っていたいという欲求と黙っているのが怖いという心理が相争うことによって吃音が起こると説明した。
これら吃音予期闘争説を唱える人々は、吃音の始まりや進展を、この説によって説明しようとしているが、特定の吃音についての説明はできても、すべての吃音について十分に説明できるとは言えない。しかし、吃音問題の最も重大なものは、吃音の予期とそのための闘争にあり、そこから起こる反応としての回避行動にあることは、ほとんどの専門家の間で一致した見方となっている。
» 予期反応
吃音者は話す前に、うまく話せるだろうかと不安を持つ。過去に、吃って人前で恥をかいたり、敗北感を味わった経験が、吃っている自分の姿を予期させ、不安を大きくする。吃るかもしれないという予期→予期どおりに吃る→さらに強い予期→さらにひどく吃る→いっそう強い予期、この悪循環が発展し、吃音者の予期不安はさらに強固なものになっていく。ついには、話さなければならない場面に一切出られない状況まで吃音者を追い込んでいく場合がある。
次のような経験を持つ吃音者は少なくない。
自己紹介が始まった。私は8番目だ。だんだんと自分の番が近づいてくる。胸の鼓動は高まり、前の人がどのように自分を紹介しているのか、ほとんど耳に入ってこない。自分の番が終わってやっと落ち着き、その後の自己紹介が耳に入ってきた」
この予期反応は、朗読や自己紹介の番が回ってくるという、比較的近い将来に起こり得る事態に対して生じるだけでなく、もっと遠い将来にまで及ぶ。たとえば、次のような場合である。
「友人の結婚式の祝辞を依頼され、断りきれずに引き受けたが、2カ月後の結婚式のことを思うと食事が喉を通らない」
吃音者がさまざまに抱いている吃音の悩みは、この不安という形で表れる予期反応に負うところが大きい。
予期反応を形成する悪循環を断ち切るにはどうすればよいか? 比較的、予期反応が小さい場面を考えてみれば、ヒントが得られる。
周囲が吃っている人ばかりの、たとえば民間矯正所や吃音者のセルフヘルプ・グループの集まりなど、吃っていることがあたりまえの状況では、予期反応は比較的少ない。吃音者が大勢の人の前で吃音の体験を話す演説練習が行われたことがある。この場合、これは練習であり、聞いている人は見知らぬ人ばかり、吃音の訓練なので吃って当たり前という気持ちがあるので、吃音からくる予期反応は少ない。これらのことから、予期反応への対策は、吃音を公表してしまうことであると言える。周りの人が、この人は吃って当たり前と思うように、話す前に吃ることを公表してしまう。公表したことから、吃ってもともとだと気が楽になり、予期反応は少なくなる。
» 場面恐怖
吃音者は特定の場面を恐れる。ある特定の場面で吃って失敗し、周囲の人から笑われたり、軽蔑されたりした嫌な経験の積み重ねによって、場面恐怖は形成される。
吃音児が不安を持ち、恐れる特定の場面の代表として、国語の時間の教室があげられるが、年齢がすすむにつれ、社会生活の範囲が拡大し、吃って失敗する嫌な体験も増える。ある吃音児は、不安や恐れを感じる特定の場面を、次のように、不安の高い順から並べた。
K君の不安階層表
1.学級のみんなの前で発表する
2.自分から人に電話をかける
3.誰もいないとき電話が鳴り、自分が電話に出る
4.職員室へ入って先生に用事を伝える
5.学校でA先生に「おはようございます」とあいさつする
6.綾部駅で「梅迫までください」と言って切符を買う
7.家の人と話をする
8.学校からの帰り道、友達と話をする
就職の面接試験や見合いで、吃って失敗した吃音者が、以後、同じような場面には一切出られなくなる場合がある。電話をかけて一言も声が出ないままに、電話を切られたり、なんとか声は出たものの、「忙しいんだ、早く言え」とどなられたのをきっかけに、以後、電話をかけられなくなる。自己紹介が嫌さにサークルに入りたくても入れなかったり、レジで買いたい品物を渡せばいいだけのスーパーマーケットでしか買い物ができない吃音者がいる。大勢の職員の前、結婚式でのあいさつなど、吃音でない人でも、あまり出たくないような場では、吃音者が場面恐怖を持つであろうことは、ある程度予想がつく。しかし、吃音でない人の予想を越える場面がある。吃音者の電話恐怖は、吃音でない人の予想以上のものであり、電話で済ませられる時でも、電話が嫌さに、わざわざ時間をかけて直接伝達に行く例も稀ではない。多くの人々が楽しく話し、歌う場に恐怖を感じ、出て行けない人がいる。これらの場に出て行かなくなるから、これらの場での経験が乏しくなり、さらにその場が苦手になり、恐怖を強めていくという悪循環に陥ってしまう。恐怖を抱く原因になっている吃音そのものが治ってしまえば、それらの場に出て行けるかもしれない。しかし、治るのを待っている間に事態はますます悪化する。特定の場面に出て行けない、つまり日常の生活の中での回避の行動が続けば、社会人としての責務を十分に果たしていないことになり、ますます劣等意識を強めていくからである。
この悪循環を断つには、場慣れをする他に方法はない。
K君が恐怖を抱く場面を困難の程度によってリストアップしたように、自分の場合をチェックしてみよう。易しい場面から徐々に難しい場面に、自分を励まし、出かけて行くことである。漠然と出て行くより、自分のリストの順に恐怖に直面していくことによって、少しずづ自信がついてくるものである。
とにかく、いろいろな場面に徐々に出て行くようにし、吃りながらも目的を達成する。他人の笑いの中に軽蔑を感じることがあるかもしれない。それらの周囲の人々の反応に対する耐性も身につける必要がある。また、過去に体験した周囲の人の嫌な反応は、たまたまそのときだけのものだったかもしれず、次の機会にはまったく違った反応が返ってくるかもしれない。自分から動き始めなければ、何事も起こらない。
» 吃語恐怖
吃音者の感情で最も共通しているのは恐怖である。恐怖とは不安の予期に他ならない。この予期は、あいまいなものから確信といえるほどのものまで幅広い。
ジョンソンは、吃音者が吃る語をどれだけ予想できるかについて研究した。彼は、吃音者にこれから話そうとする語に、(1)吃る (2)おそらく吃る (3)吃らない という三通りの予想を立てさせた。その結果、吃音者は、吃ると予想した語の88%を吃り、吃らないと予想した語の 0.4%を吃るということが分かり、予想の度合いと実際に吃る度合いは確かな関係があると報告した。また、世慣れした吃音者は、ナイーブな吃音者よりも予想がはずれるという結果も出た。
一方、マーチンらの研究では、吃るであろうと予想した語と、吃らないと予想した語を比較すると、吃ると予想した語で吃ることが多かった。しかし、吃ると予想した語に関しては、予想の半分も吃らなかったと報告した。以上のことから、吃語恐怖と実際に吃ることとの間には関係があるものの、完全ではないということが共通理解になっている。
実際に、自分の名前で極端に吃ったり、タ行カ行音を極度に吃る吃音者は多い。そのような音や単語をどうしても使わなければならない場面では、吃語恐怖のために非常に不安定な心理状態になる。吃るかもしれないという恐れから、吃音者は、とっさに言い換えをして避けるが、固有名詞のように言い換えのできない語に吃語恐怖を抱いている場合、深刻な問題となる。普段は比較的楽に話せる人が、自分の名前が言えないために、裁判所に苗字の変更願いを出したことがあった。
» おわりに
「社会に積極的に出て行けない、不安や恐れの強い吃音者に、それができるように少しでも軽くしてあげることを第一に考えなければならない」と主張する臨床家は多い。しかし、吃音への不安や恐れは、吃症状の軽重でははかれない。症状が重くても不安や恐れの少ない人がいる一方、症状がごく軽くても不安や恐れの非常に強い人がいる。症状の重い人がどこまで軽くなれば、また、症状の軽い人がどの程度さらに軽くなれば、吃音の不安や恐れが減り、積極的に社会に出て行くことができるのか。吃音者の要求は際限がなく、完全に治るまで追い求めていく。どの線で納得するか、納得させるか、非常に難しい。吃音が軽くなるまで社会に出て行けないのであれば、それまでの社会生活がおろそかになってしまう。実際には、その吃音者の症状が重くても軽くても、不安や恐れが強くても日常生活は続いているのである。
吃音者が、吃るからといって恐れている場に出なければ、ますます不安や恐れが強まり、そのような場に出て行けなくなる。この悪循環を断つには、苦しくても不安や恐れに直面しなければならない。
具体的に次のようなことから始めよう。
・不安や恐れを抱く場面をリストアップし、それに順位をつける。易しい場面から難しい場面に徐々に慣れるようにする。
・教室や集会室では、必ず前の席に座るようにする。
・人の集まるところへはできるだけ出かけて行く。ただ黙っているだけでもよい。
・体をリラックスさせる方法を何かひとつ身につけておく。呼吸法、自律訓練法、ヨガ、ストレッチ、エアロビクス、禅、太極拳など
・不安や恐れのある場面で話さなければならなくなったときは、「私は吃りますが・・」とまず自分の吃音を公表する。それだけで吃ってもともとの気持ちになり、ずいぶん楽になる。
・明るい表情、明るい声で、明るく吃ろう。