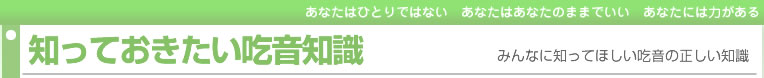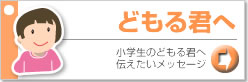チャールズ・ヴァン・ライパーの吃音方程式
» はじめに
ウェンデル・ジョンソンと並び、その業績が評価されている吃音学者にチャールズ・ヴァン・ライパーがいる。ヴァン・ライパーは、研究者というよりは臨床家としての立場を重視した。有効な治療法を開発しようと20年以上にわたって吃音の臨床に携わり、それを自ら評価し、検討を続け、修正を加えていった。
彼は、治療の目的を吃らずに話すことではなく、なめらかに吃ることにおいた。これまえ開発されてきたさまざまな治療法がまったく効果がなく、彼自身が試みた臨床経験からも完全に治ったという例はほとんどないという。しかし、なめらかに吃ることができ、吃音をハンディとせずに生きる吃音者が育ってきたのである。
彼は、吃音の重症度を評価するために方程式を提示し、それを基にした治療計画を示した。それに基本的に共感しながらも、私たちは、さらに吃音者自身の人生に踏み込み、吃音と上手につきあうの観点から、もじって方程式を試案してみた。
ヴァン・ライパーの方程式と私たちの程式を紹介しよう。
» チャールズ・ヴァン・ライパーの吃音方程式
吃症状に波があるのは、吃音者であれば誰でも経験する。独り言を言うとき、小さい子どもに話しかけるときは、比較的吃ることが少なく、何かで憂鬱な気分になっているときはよく吃る。それはなぜだろうか。この吃音の波現象を分かりやすく理解するために、さらに吃音を評価するために、ヴァン・ライパーは方程式を作成した。吃音を悪化させる要因を分子とし、吃音を軽くする要因を分母として、吃音の重症度を表す方程式とした。この方程式を基に吃音の治療計画を立てた。つまり、吃音を悪化させる要因(分子)を減少させ、吃音を軽くする要因(分母)を強化していけば、吃音は軽くなっていくというのである。
方程式は次のようなものである。
(PFAGH)+(SfWf)+Cs
吃音の重症度=
M+F1
1.分子(吃音を悪化させる要因)
P(Penalty 罰)
-吃ったときに与えられた罰、または、その経験の記憶-
吃る度に嫌な顔をされた、電話で吃っていて途中で切られた、「もっとちゃんと話さんか」と叱られた、体育の時間に吃って号令がかけられず教師になぐられた、などの体験を持つ吃音者は多い。これらの嫌な体験は吃音を悪化させる。
F(Frustration 欲求不満)
-欲求不満を感じるとき、または、記憶に残っているすべてのタイプの欲求不満-
学生時代、指名されたとき、答えが分かっていても「分かりません」と言ったり、間違った答えをわざと言ってしまったりした経験。話したくても話せない経験などは、欲求不満を募らせ、吃音を悪化させる。
A(Anxiety 不安)
-不安があるとき-
吃って失敗した過去の経験から、また吃るのではないか、吃って失敗するのではないかと、話す前に不安を持つ吃音者は多い。この不安が大きくなると回避行動につながる。
G(Guilt 罪)
-罪の意識-
吃るたびに母親が悲しそうな顔をする、子ども心に母親を悲しませてはいけないと思い、吃音に対して罪の意識を持ってしまう。会社の受付や電話のよくかかる職場で、吃って応対すると会社のイメージを悪くするのではないかと悩む吃音者がいる。まじめな人であればあるほど、この罪の意識を募らせる。
H(Hostility 敵意 攻撃心)
-はけ口の必要な敵意-
恥ずかしい、申し訳ないという恥や罪の意識が昂じると、自分自身に対しても、聞き手に対しても敵愾心を持ってしまう場合がある。この言いようのないいらだちは、はけ口を求めても得られず、さらに吃音を悪化させていく。
Sf(Situational fear 場面に対する恐れ)
-過去の不愉快な経験に基づく場面に対する恐れ-
国語の朗読の時間、吃って立ち往生したり、研究発表のとき吃って失敗したり、結婚式の挨拶で吃って恥をかいた経験は、吃ることへの恐れを強化する。何度も何度もそのような失敗の経験を重ねると、それらの場に出ていけなくなるほどの恐怖心を持つようになる。特定の場面に対して恐れを持つ吃音者は多い。
Wf(Word fear 語に対する恐れ)
-過去の不愉快な記憶に基づく特定の音、または語に対する恐れ-
自分の名前、その他の固有名詞、など特定の音でたびたび吃った経験によって、発音しにくい音を意識する。吃るかもしれないと予期し、実際に吃ってしまうことによって、特定の語に対する恐れが強化される。
Cs(Communicative stress 話すことに対する心理的圧迫)
-話すことに対する心理的圧迫の大きい場面、あるいは重要なことを言わなければならないとき-
大勢の人の前や改まった席で話さなければならないとき、または重要なことを伝言しなければならないとき、正確に伝達しなければならないとき、など心理的圧迫は大きい。
2.分母(吃音を軽くする要因)
M(Morale 士気)
-自我の強さ、自信、安定感など-
吃音者は自信を持っているときはあまり吃らない。仕事や人間関係に自信を持ってあたっているとき、また何か目的を持てたとき。
Fl(Fluency 流暢さ)
-本人の感じる流暢さの程度-
本人が、吃りながらもなめらかに話せたという満足の経験を重ねる。
» 伊藤伸二の吃音方程式
吃音は、吃音症状が軽くなればというような単純なものではない。
吃音によって自分の行動や人生を左右されずに生きている人がいる一方で、吃ることを嘆き、恐れ、自分の殻の中に閉じこもり、不本意な生活をしている人がいる。
吃音の症状の重症度で、単純にその人を論じることはできない。吃症状に波があるのと同様に、吃音者の吃音に対する態度や悩みにも波がある。私たちは、この吃る人の悩みの実態を調べるために、全国を巡回して相談会をすると同時に、アンケート、面接調査を行い、「吃音と意識の調査」を行った。そのたくさんの調査結果からも、吃音が重かった時期と吃音の悩みが深かった時期は必ずしも一致しないということが明らかになった。吃っている事実は変わらないのに、吃音に大きく影響を受ける人と、そうではない人がいることにも注目した。ここに、吃音へのアプローチのひとつの方向を見いだすことができる。吃症状と悩みとの関係の調査で次のことが明らかになった。
「吃音に悩むことが多かったのはなぜか?」
「吃ることが多かったから」という答えよりも、「いつも気分が沈んでいた」「将来に不安があった」という答えの方が多かった。
「吃ることが多かったのはなぜか?」
「対人関係が悪かった」「相談相手がなく、劣等感が強かった」などの答えが挙げられた。
「吃音に悩むことが少なかったのはなぜか?」
この質問に対する答えは、一層興味深い。「吃ることが少なかった」という答えよりも、「熱中するものがあった」「仲のいい友達がいた」「他のことで自信があった」という答えの方が多かった。これらの調査結果から、吃症状に焦点をあてていたこれまでの吃音問題解決のあり方から、吃音者自身の意識と行動に焦点をあて、問題解決を図ろうとする方向へと転換していった。これらの調査、および面接調査などの中から、私たちの吃音方程式が作成された。
吃音が大きな問題となる要因を分子とし、問題となるのを防ぐ要因を分母とした。分子として挙げられている要因を、よりよい方向へ持っていき、分母として挙げられている要因を強化することによって、吃音とうまくつき合う方向が探れると考えた。
1.分子(吃音のとらわれを強める要因)
人間関係の狭さ
幼少時の愛された経験の少なさ
吃って失敗した経験の質と量
日常生活の中での話すことから回避の度合い
吃音のことを話せる人がいない
レジャー活動の貧困さ
吃音も含めたさまざまな劣等意識
2.分母(吃音の解放を進める要因)
豊かな人間関係
楽天的な人生観
明確な人生目標
吃ってでもできたという経験
仕事や学習についての自信
人に受け入れられた経験
» おわりに
チャールズ・ヴァン・ライパーの方程式も、私の方程式も、分子、分母については吃る人それぞれによって、項目が違ってくるであろう。その人にとって特に重要な項目もあれば、反対に意味のない項目もあるだろう。さらに項目を付け加えなければならない場合もある。これらを参考に、自分自身で、またはグループで、自分のこれまでの人生を振り返って、自分自身の方程式を作ってみよう。自分で作った方程式だ。きっとやる気が出てくることだろう。皆がその方程式をもちより、多くの人と検討すると、さらにいいものに作り替えることができるかもしれない。